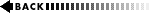三ッ木の覚え書き
最初の一歩は中学の林間学校で書いた一編の詩が『過程』という校内雑誌に掲載されたことだ。
小学生の頃は絵を描くことが好きで、美術の時間が楽しみだったが、
入学したある大学の付属中学は体育会系で、芸術は片隅に追いやられていた。
その一編の詩は生物の哀れを書いたものであり、教員室へ呼ばれて担任からお褒めに預かった。
校内誌が手元にないのが残念だ。自分の書いた詩が活字になったが感動はなかった。
父親から殴られた。ラーメン屋の跡取り息子に詩は必要ないというのが理由だった。
父親には殴られた記憶はあるが優しくされた記憶は一切ない。
スパルタ教育というよりも虐待に近かった。
高校に進学すると、すぐに美術部に入った。
油絵をよく描いたが、顧問教師に上野のクロッキー教室へ連れて行かれた時は恥ずかしかった。
全裸の女性が出てきたからだ。周りには禿オヤジが食い入るように見つめている。
同類に思われているかもしれないと思ったが、結局は同類だった。
美術の顧問教師は藝大の日本画家を出たばかりだったが、教えてくれたのは抽象画だった。
エルンスト・フィッシャーの『退廃と芸術』の読後感で『秀』をもらった記憶がある。
美術部に在籍しながらも、興味は萩原朔太郎やランボー、ボードレールの詩だった。
暗唱しているほど好きだったのはランボーで、『地獄の季節』がたまらなく好きだった。
このころ詩をノート10冊ほど書いて、それは今でも手元に残してある。
高校生の頃、釣り好きの父親に連れられて毎夏、伊豆大島の船宿へ行った。
そのころの大島は、水はきれいだった海岸が岩だらけだった。
湘南の砂浜をうらやましく思った。
父親と一緒に釣り船に乗り、かったくりという竿を使わない方法で糸を垂らしていたら
ゴンゴンというアタリがあり、父親に告げると真剣な顔でそばへ来てテグスを奪うと、
ぐいぐいとしゃくりあげた。12キロの大鯛で、翌日のスポーツ新聞で取り上げられた。
船宿の常客に林房雄がいた。林先生は、浴衣の前をはだけて●●タマ丸出しの格好で、
夏でもクサフグの鍋をつついていた。
何度か食事の席をともにさせていただいたが、気さくな人というイメージだった。
釣り宿の常客には、児玉誉士夫がいた。常にボディガードを引き連れていた。
夏でもボディガードは上着を着て、懐に手を差し込んでいる姿に興味を持った。
父は開高健を林先生に紹介されて訪れたようだが、会ってもらえなかったとがっかりしていた。
釣りのクラブへの入会をお願いしに行ったのだ。
大学進学時、たまたま受けた推薦直前の試験で数学と化学の成績が良かったので、
担任から農学部へ行けと言われた。今考えると、食堂の跡取り息子だったので農学部でもよかったかもしれないが、
当時は詩的少年だったので、せめて経営学部へ行かせてほしいと懇願したが叶わず、
「だったら文学部でいいです」と見えを切った。ただ単に農学部のある校舎が遠かったこともあったし、
大学の教授面接にも自信がなかった。
農学部へ推薦され、教授から「米を英語で何と言いますか」と聞かれた者がいた。
突然のことにその生徒はわかりませんと答えた。
すると面接官は嗤いながら、「じゃあリンゴは英語でなんて言うのかな」と生徒に聞いた。
生徒は腹を立てて答えなかったら推薦不合格になった。
そういう話も伝わっていたので、推薦に関しては用心していた。
推薦面接時に、藤村の『若菜集』を知っているかと中山和子先生に問われたが、「若菜集」は知らなかった。
踏ん張りどころだった。切羽詰って『僕は萩原朔太郎の「月に吠える」が愛読書です』と言って難を逃れた。
大学へ進学すると、通っていた大学の教授連には著名文学者が多く、
ゼミは山本健吉に教えられ、卒論は平野謙に教えを乞うた。
中村光夫や大岡信、本多秋五の授業も受けたが、本多秋五以外の授業は面白くなく、欠席が多くなった。
ゼミの山本先生には、高校時代に耽溺したフランスの詩人と芭蕉の句を対比させた発表をして、
気難しい先生からお褒めの言葉を頂戴したが、興味はギョームアポリネールだった。
卒論は、夏目や太宰などは希望学生が多すぎたので、
開成に通っていた弟が図書館から借りてきた吉行淳之介が面白かったので、
吉行を選んだ。全集の巻数が少ないのもありがたかった。
卒論を指導した平野謙は吉行をあまり評価していなかったことを知るのは、大学を卒業してずいぶん経ってからだ。
卒業後に知己を頼ってもぐりこんだ出版社で、まだ無名の松本邦吉氏と一緒になった。
松本氏とはお互い吉行ファンということで、意気投合し、以来40年以上の付き合いをしている。
山本先生からお褒めの言葉をいただいたにもかかわらず、
俳句には全く興味がわかなかった。
松本氏になにか書いてみろと言われて戯作を書いたりしたが、
ここに発表するほどの出来の作品ではない。
松本氏が退社したのち、自己流で小説を書いていたが原稿用紙に書いた小説はどうにも頼りなく見えた。
30代になるとワープロが出始めたがまだ手の届く価格ではなかった。
出版社を辞める直前に、ブラザーから安価なワープロが発売され、家の者に購入したいと言ったが拒絶された。
あのときワープロを手にしていたら、小説を書きあげてそれなりの成果を出していたと思うが、
この歳になっては後の祭りだ。
その後、営業次長からの執拗な虐待に耐えかねて、13年勤めた出版社を辞し、
印刷屋の社長から誘われたこともあって転職した。
ちょうどコンピューターが発売されたころだ。印刷会社では、校正の仕事くらいしかなく、
印刷物の運搬という、なかば肉体労働をしていたが、その会社ではOBCのPCソフトのマニュアルを制作していた。
そこで、キャノンのEZPSという写植機とコンピューターの機能を備えた機器を使った。
念願のワープロも入手できた。
ワープロの力は絶大で、書いた小説が活字になった際にどこが悪いかが簡単にわかるような気がして
一気に書いたのが『バス亭』だった。オール読物の新人賞に応募し、落選するのがオチと思っていたが、
中間発表で予選通過者の氏名の掲載されたページを見ると、あった。
それも、太字だったので2次予選を通過している。望外の喜びだった。
父親に掲載誌を見せると、生まれて初めて褒められた。
「俺も書いていたが、最後まで書けなかった」と言われ、「なんだよ、親父も文学青年だったのかよ」と思った。
初めて書いた小説がいきなり2次予選を通過したのは25年ほど前のことだ。
そうなると、印刷屋の仕事がバカらしくなり、次作に没頭する。
丁度、愚息が中学受験を控えていたので、それを題材にした小説を書いて応募したが、
翌年の選考では1次予選しか通過できなかった。
愚息は麻布に進学した。奇しくも吉行の母校だった。
ところが、印刷屋の社長の息子が筑波大付属に小学校に通っており、
愚息が筑波大付属を蹴ったのが面白くなかったのかいきなり解雇された。
三顧の礼で迎えられた印刷屋を解雇されたのだ。
いい歳になっていたので再就職には苦労したが、そんなときに拾ってくれたのが、
ムショから出たばかりの『致知』の竹井博友氏だった。
巨額の脱税でムショ暮らしを余儀なくさせられ、出てきて致知とは別の出版社を立ち上げていた。
竹井氏に認められ、ライターとして仕事を始めた。不遇な過去を持つ人のドキュメントを3ページほど任された。
いろいろな人に会って、様々な記事を書いたが、そのうちの一人に悟道軒圓玉師匠がいた。
暑い盛りに世田谷の奥地へ取材に行き、エアコンのないトタン屋根の下でテープを回したが、
途中でテープレコーダーの電池が切れてしまい、遠くのコンビニへ走った記憶が昨日のことのように思い出される。
圓玉師匠はかつては天才とまで持て囃された講談師だったが、交通事故による脳の高次機能障害で、
持ちネタのすべてを失ったという、不遇の方だった。持ちネタは失ったが、そのときの境遇を語る熱い気持ちがこちらに伝わり、
記事はいいものになった。
その後、失明した料理人や母と生き別れた税理士へのインタビューをした。
最後に東京相互の長田庄一の自伝の執筆を依頼されたが、
その時は不安定なライター生活よりも安定したサラリーマン生活を求め、
自宅近所の印刷会社に職安の紹介で再就職していたので辞退した。
再就職先の印刷会社で驚いたのは、社長がとても傲慢不遜で、
なおかつ社長夫人が経理のお目付け役、二人の息子が社員という、
よく言えば家族的、悪く言えば超同族会社であることだった。
加えてサンドという製薬メーカーを自己都合で退職した営業部長がおり、
いきなりその部長に駐車違反の身代わりを頼まれたのには度肝を抜かれた。
ずいぶん遵法意識に欠ける人間がいるものだと、驚かされたものだ。
免許を書き換えたばかりでもあり、いきなりゴールド免許の権利を喪失したので腹が立った。
サンドに1年くらい営業に行ったが、すぐにチバ・ガイギーと合併して、ノバルティスファーマという会社になった。
合併時には、ずいぶんたくさんの仕事を受注した。
青山のノバルティスには毎日通った。地下駐車場の管理人や受付嬢とはすっかり顔見知りになった。
自分は文学を志すよりも営業に向いているのではないかと思ったのは、
個人の年間売り上げが1億3000万円を超えたからだ。
それでも文学の道を閉ざすことはできず、ポツポツと小説を書いていた。
『サイドビジネス』という長編を書いたのはそのころだ。
駄作に終わり、小説現代の新人賞はかすりもしなかった。
多忙な中での執筆は筆が荒れた。
その印刷会社は薬品メーカーの仕事が多く、医薬系エージェントの仕事もあった。
分厚い医学書の印刷時には出版社での経験が役に立った。
MITというエージェントがあり、そこの社長とはしばらく親しくしていたが、
駐車違反の身代わりを頼んだ営業部長が直接の取引をエスエス製薬に持ちかけて、
怒りを買った。
MITの社長から、独立して一緒にやろうと持ちかけられたが、30%のキックバックを要求されて無理だと思った。
そのときはもう、MITの売り上げが80%を超えていた。もう仕事は出さないといわれて、思い切って独立した。
独立しては見たものの、特別のクライアントがないので苦労した。
サラリーマン生活が長すぎたので、経営はずぶの素人に近かったからだ。
一緒にやっていこうといわれたのは、MITの営業からだった。
その営業はMITから独立して会社を興した。そこには印刷会社時代の営業部長がいたので、
再び驚いた。
(続く)